日本の医療制度の特徴とは|海外との違いを真野俊樹先生が解説
2024.01.12

国民皆保険制度がある日本では、誰もが安全で質の高い医療サービスを安価に受けることができます。しかし諸外国の医療制度と比較すると、これは決して当たり前のことではありません。
今回は、世界各国の医療経済について第一線で研究されている真野先生を迎え、日本と海外の医療制度の違いについて、さらにそこから見えたより良い医療のあり方や、一人ひとりが持つべき意識について教えていただきました。
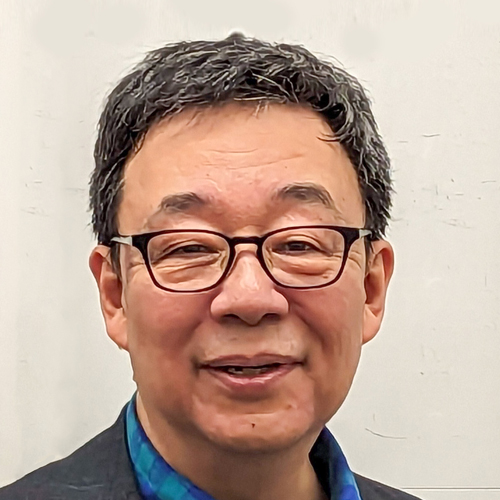
真野 俊樹 教授
中央大学大学院 戦略経営研究科 教授
多摩大学大学院 MBA特任教授
1987年に名古屋大学医学部を卒業後、糖尿病内科医として臨床経験を積み、1995年に米コーネル大学医学部に研究員として留学。その後、製薬企業のマネジメントに携わりながら英レスター大学大学院でMBA※を取得。現場主義の研究スタンスで、諸外国における医療制度や医療経済について長年現地調査を行う。医学博士、経済学博士、総合内科専門医と多様な顔をもち、医療政策・医療経済における著書も多数。
※ MBA(Master of Business Administration):専門職学位であり、日本では経営学修士とも呼ばれる。
日本の医療を取り巻く社会構造と意識の変化

日本の医療提供について、現在に至るまでの経緯を教えてください。
日本では、病気や事故に見舞われた際に、いつでも・誰でも必要な医療サービスを受けることができます。当たり前のことに思うかもしれませんが、これは医療費の負担を軽減してくれる国民皆保険制度があるからこそです。皆保険が制定されたのは1961年、戦後の復興の最中で医療資源が不足する時代でした。誰もが必要な医療を受けられる環境整備が一気に進む中で、焦点が当たったのが民間の医療法人です。ヨーロッパのような海外では、多くの医療機関が国主体である一方で、日本では民間による医療サービスが拡充していったことが特徴の一つといえます。
今では全国に病院や診療所が充足し、すぐに医療機関を受診できる環境が整いました。その裏付けとして、日本は人口当たりの全病床数で世界一を誇っています(厚生労働省「医療提供体制の国際比較 OECD加盟国との比較」2022年)。医療レベルにおいても、近年次々と発表されているがんの手術後や脳梗塞発症後の生存率に関する論文比較からも分かるように、さまざまな領域で世界トップクラスの対応がなされているといえます。
現在、日本の医療を取り巻く環境はどのように変化しているのでしょうか?
近年の大きな潮流として挙げられるのが人口構造の変化です。2025年には団塊の世代が75歳を迎え超高齢社会がさらに進むと考えられており、全国の病院を集約・再構築する動き――いわゆる地域医療構想が進められるなど、医療の提供体制に大きなインパクトを及ぼしています。
高齢者がメインターゲットとなる中で、「治療の性質」も変化しつつあります。例えば、若年層にとっては「治す」ことが主目的となる一方で、高齢者の場合は、いかに疾患と「併存」しながら、人生をより良く生きるかに重点を置く考え方が増えています。つまり、「疾患が治ればよい」という単純な話ではなく、治療を前提に、ウェルネスのような上位概念を求める時代になってきているのです。
現在の皆保険制度は、基本的に病気になった際の治療費をサポートする仕組みのため、予防・未病段階は範囲外といえます。そうした変化に伴うニーズにどう対応していくかは、今後、模索していく必要があるのではないかと考えています。
日本の医療は「うまい、安い、早い!」の三拍子?

先生の主なご研究について教えてください。
医療経済においては、一つの国に特化した研究をされている専門家が一般的かと思いますが、私の場合は各国における医療制度の国際比較が主な研究領域となります。2017年に刊行した著書※の中では、医療を支える6つの柱「医療レベル、医療の身近さ、薬の依存度、医療費、病院、高齢化対策」について、それぞれ「患者・医療機関・社会保障費」の3指標を定めて行った比較研究について紹介しています。また、医療提供者・享受者間の理想的な関係性を主な議題とした医療マーケティング分野や、アフターコロナで需要が高まっている医療ツーリズム分野についても研究しています。
※ 『日本の医療、くらべてみたら10勝5敗3分けで世界一』講談社(2017)真野俊樹著
海外との比較から見えた、日本の医療の優位性と課題点について教えてください。
客観的なデータに基づいて見てみると、日本の医療レベルはかなり高い水準にあるといえます。先述したように、日本では低い自己負担で常に一定レベルの診察が受けられますが、各国に目を向けてみるとどうでしょうか。日本のような保険制度ではないアメリカでは、高度な医療を受けるためには高額な自己負担を強いられますし、ヨーロッパでは決められた「かかりつけ医」をまず受診するため、予約から診察までに期間を要することもあります。
病院や病床の数が多いことも日本の利点といえますが、近年は在宅医療にシフトしていくべきだという考え方も出てきています。日本の病院は、ケアが行き届いていて安全に長く滞在できるという認識が浸透しているため、重篤な時期を過ぎても入院を続ける患者さんも多く、こうしたニーズへの対応も十分な病床数に起因していました。
しかし近年は、高齢者が増加する中で、暮らし慣れた自宅で医療を受けたいという要望も高まっています。日本の在宅医療は、医者や看護師が定期的に患者宅を訪問するという世界的に見ても特殊な発展をしているため、オペレーション効率を担保しながら患者さんのQOLを叶える医療をいかにして実現するかが、今後の課題になってくると考えています。
また、地方に点在している中小病院の人手不足や財政難も、直面している問題の一つです。病院の集約は超高齢社会への対応としてだけでなく、民間病院の存続や医師の勤務体制の効率化につながる施策としても必要性が高まっています。
コロナ禍で見えた「異常事態」への向き合い方

各国の比較軸について、コロナ禍を経て変化した部分などがあれば教えてください。
基本的な考え方に大きな変化はありませんが、コロナ禍への対応から浮き彫りになった各国の特徴や実態は、過分にあると思います。感染症は主に公衆衛生学などで研究されてきましたが、先進国における研究対象としては、がんや認知症、生活習慣病などがこれまでは優先されてきました。今後、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のような感染症が出現する可能性は大いにありますし、COVID-19も完全に収まったわけではありません。今や感染症対策は国としても非常に重要となるため、ともすれば「高齢化対策」の次に「感染症対策」の軸を追加することも検討すべきかなと思います。
「浮き彫りになった」とは……例えばどのような特徴でしょうか?
例えば、イギリスの医療制度では、決められたかかりつけ医の診察を受けた上で、次のステップとして専門医のいる病院を受診するよう定められています。しかしながら、かかりつけ医ではCOVID-19に対応しうる医療資源が十分にないため、大規模な急性期病院が一時的に対応することになりました。そうした意味では、従来の制度では感染症に対応できなかったといえます。
また、ドイツは、日本と似たような公的な保険制度があるため、かかりつけ医の選択肢もイギリスよりは広がります。ドイツではかかりつけ医、すなわち地域の開業医がCOVID-19に関わる診療の大半を引き受けたことで、大病院にCOVID-19罹患者が殺到する事態を避けることができました。
日本では、最終的には民間病院もCOVID-19罹患者を受け入れたことで医療崩壊を防ぐことができましたが、パンデミック初期の頃は、感染者数が少ないにもかかわらず入院できず、病床が不足する事態が起きました。
こうしたCOVID-19に対する各国の対応を比較することはできても、果たしてどれが正解だったかを一概に語ることはできません。感染者・死亡者数から「成功した」という見方ができたとしても、視点を変えれば経済を止めた、制限が長期化したといった見解と表裏一体であるからです。紛糾するテーマであることは当然のことといえます。
「医師の領域」という固定観念を超えて

真野先生の今後の研究における展望を教えてください。
高度な医療にどこまで保険を適応させるかなど、医療における費用対効果は、重要なテーマの一つとして注目しています。例えば、がん患者が一年延命するための治療薬として支払える許容範囲はいくらなのか、ということになるのです※。また、政府が医療DXを推進しているように、ITが医療のあり方を今後どう変えていくのかも非常にホットなテーマですので、医療マネジメントの視点から突き詰めていきたいと考えています。
※ さらに詳しく知りたい方は、『「命の値段」はいくらなのか?“国民皆保険”崩壊で変わる医療』 角川書店(2013)真野俊樹著をご参照ください。
そもそも、真野先生が臨床医を経て、医療マネジメントの領域に進まれたきっかけは何だったのでしょうか?
私が臨床医として働いていた当時は、目の前の患者さんのために最善を尽くすことが全てで、医療費や効率面を考慮する必要はないという前提が、日本の医療現場には浸透していました。しかし、1995年にアメリカへ留学した際、国民皆保険がないアメリカでは金銭的な理由で必要な医療を受けられない人がいるという現実を目の当たりにしました。その実態に疑問を持ったことが、医療制度の国際比較という現在の研究につながっています。
日本では、「治療ができる/治療を受けられる」環境が当たり前だと思っている人がほとんどかと思います。身体に何らかの不調を感じた時に、自分で調べるよりも「とりあえず医者に行けば良い」という考え方が染み付いているように思います。日本の医療が充実しているがゆえの習慣のため、決して悪いことではありませんが、裏を返せば医療に対する自己解決能力の欠如につながっているともいえます。

では、医療におけるヘルスリテラシーを高めながらより良く生きていくために、私たちは、どのような意識を持つべきでしょうか?
医療現場における、ある種のパターナリズムがしばしば問題視されるように、特に日本では医師に治療の決定権があり、患者は受け入れるのみという一方通行がスタンダードとなっています。一方、アメリカでは、どの保険に入り、どの治療を行うかという選択が、自分の命を左右するといっても過言ではありません。だからこそ、自身の健康状態を把握し、医療制度を自らキャッチアップしていこうという姿勢があります。
このように、将来の健康を自分自身で守っていく意識が必要であることは、日本の医療においても例外ではありません。そのためには、病院側もさらなる患者目線の医療提供が求められます。寄り添う医師をアドバイザーに、自身の身体状態やそれに合った医療を把握しながら、自分自身で健康へ向かう舵を取っていく。それが一人ひとりのウェルビーイングにもつながっていくと考えています。



