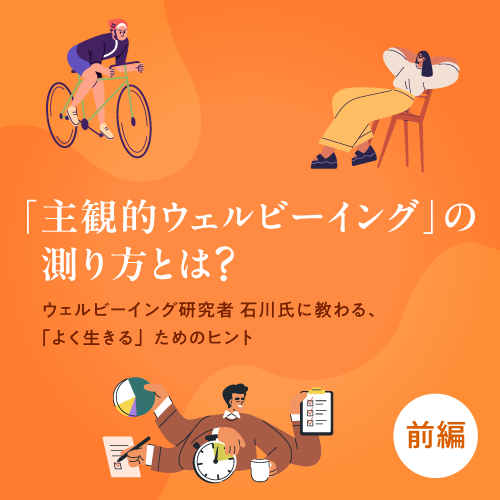「主観的ウェルビーイング」の測り方とは?ウェルビーイング研究の第一人者、石川氏に教わる、「よく生きる」ためのヒント[後編]
2024.12.20

人生100年時代といわれる今、人々は「物質的な豊かさや地位」を優先する従来の価値観から脱却し、それぞれの価値観に根ざした幸せや豊かさを模索し始めています。しかし、多様化し複雑さを増す社会では、それぞれの幸せを見つけることはより難しくなっているともいえます。
このような現代において、「ウェルビーイング」はサステナブルな社会づくりや企業経営においても重要なキーワードとなり、産官学民から注目が集まっています。今回は、「人がよく生きるとは何か」をテーマにウェルビーイングを研究される石川先生に、ウェルビーイングの捉え方やビジネスへの応用、そして、人生をよりよく生きるためのヒントを伺いました。
前編はこちら
ウェルビーイングは企業変革の起点にも

石川先生が代表を務める公益財団法⼈Well-being for Planet Earthの取り組みについて教えてください。
当財団では、ウェルビーイングの発展に寄与することを目的に、国内外のウェルビーイングに関する研究開発活動の助成を通じて研究者を支援しています。
ウェルビーイング研究は現在、第三世代に突入していると考えています。ここでウェルビーイング研究の歴史を紐解いてみると、人類は何千年にもわたり、「幸福とは、豊かさとは何か?」「よく生きるとは何か?」といった議論に明け暮れてきました。私は、この議論を深めてきた宗教者や哲学者を第一世代と捉え、「持論の時代」と呼んでいます。
その後、20世紀に入ってから「幸福」を科学的に捉える第二世代が台頭してきました。この第二世代を一言で表すと、「ウェルビーイングの定義づけを諦めた世代」です。何千年にわたって議論してもコンセンサスが得られないなら、ウェルビーイングを定義するのではなく、自分自身がウェルビーイングな状態にあると言っている人の特徴を探ろうという方向に舵を切ったのです。自身がウェルビーイングな状態にあると言う人は、どんなに苦しい状況でも必ず存在し、その人の思考や物事の捉え方からウェルビーイングの要素を紐解くという、まさに発想の転換です。また、第二世代では、一人の人生において、ウェルビーイングな時とそうでない時の変化から、ウェルビーイングを探る研究も行われていました。
そして近年、いわゆるウェルビーイングな人の脳内で何が起きているのかを探る脳科学的なアプローチが始まりました。これ以降を第三世代と捉えています。私は第二世代と第三世代の狭間にいる立場にあると感じています。
ウェルビーイングを軸とした産業への広がりをどのように見ていますか?
ウェルビーイングは、社会実装されてこそ意味があります。私は社会実装という意味で、当初、「ウェルビーイング産業」のような、人々のウェルビーイングを創出する産業自体が形成されると予想していたのですが、今はその予想を改めています。ウェルビーイングが産業にもたらす影響としては、デジタルトランスフォーメーション(DX)がデジタル産業に限らず、あらゆる業界で事業変革を加速させたように、すべての業界においてウェルビーイング的な視点から既存事業を変革する、「ウェルビーイングトランスフォーメーション(WX)」が進むと考えています。
業界全体がウェルビーイングに向かうと最初に宣言したのは、生命保険業界でした。生命保険業界における従来のスタンダードだった緊急時の保証と将来のための資産形成だけでは、サービスが差別化できなくなり、顧客の日々のウェルビーイングをいかに維持・向上できるかに競争の軸が移行したのです。医療・製薬業界でも、患者を「治療対象者」から一人の生活者として捉えなおすことで、病院やクリニックでの医療現場を超えたサービス提供が模索されています。このように、事業活動を通して、顧客や従業員、社会といったさまざまなステークホルダーのウェルビーイングをいかに向上できるかを追求するWXの動きがさまざまな業界へと広がりつつあります。
ウェルビーイングへの鍵は「多様な居場所」と「健全な多重人格」?

人生100年時代といわれる現代をよりよく生きるためのヒントは、どのようなところにあるとお考えでしょうか?
一つは、居心地の良い場所を増やしていくことだと考えています。「居心地の良さ」には、実は二つの相反する要因があります。一つは、コミュニティの中で自分が「何者かであること」です。職場や家族の中で自分の役割や存在意義が明確化されることで、自信や安心感を得ることができます。もう一つは、逆説的ですが、「何者でもないこと」です。特定の役割や存在意義がないからこそ、居心地が良い場合もあります。例えば、自分がまだ「何者でもなかった」頃を知る学生時代の友人と過ごす時間は、気楽で心地が良いものではないでしょうか?「何者かである」自分と、「何者でもない」自分のグラデーションが一人の人間の中に存在すること――私は、これを「健全な多重人格」と呼んでいますが、こうした生き方を許容し、実践することがウェルビーイングの維持・向上につながるのではないかと考えています。
一方で、全ての人格で完璧を追い求めることは危険です。例えば、働きながら子育てをし、さらに学校のPTAまで務める女性が、全ての役割において完璧であろうとすると、精神的ダメージを受けやすいといわれおり、専門的には「スーパーママ症候群」と呼ばれています。頑張りすぎず、何者でもない自分も含めてさまざまな人格を自分らしく両立させることがポイントです。
また、人生100年時代においては、年を重ねいくつになっても、自分なりの「舞台」を持つことが不可欠ではないかと思います。大げさな舞台でなく、地域のコミュニティやお祭りのような、生き生きとした自らの生き方を表現できる舞台です。人はそうした「舞台」があるからこそ、活力が湧き、メリハリのある人生を送ることができるように感じています。ぜひ、みなさんも「何者かである自分」と「何者でもない自分」を大切にしながら、自分らしい舞台を見つけてみてください。
「ウェルビーイング」関連記事:ウェルビーイングの定義はこちら:ウェルネスとは|ウェルビーイングとの違いや世界的な潮流について| 陽だまり | 未来に、ウェルネスの発想を。 - 三井物産 (mitsui.com)(https://www.mitsui.com/wellness/163/)をご参照ください。
*1 OECD(2013)“OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being”,OECD, Paris.
*2 World Happiness Report(世界幸福度報告書): https://worldhappiness.report/data/(参照 2024-11-20)
*3 Perspect Psychol Sci. 2008 Jul;3(4):264-85.